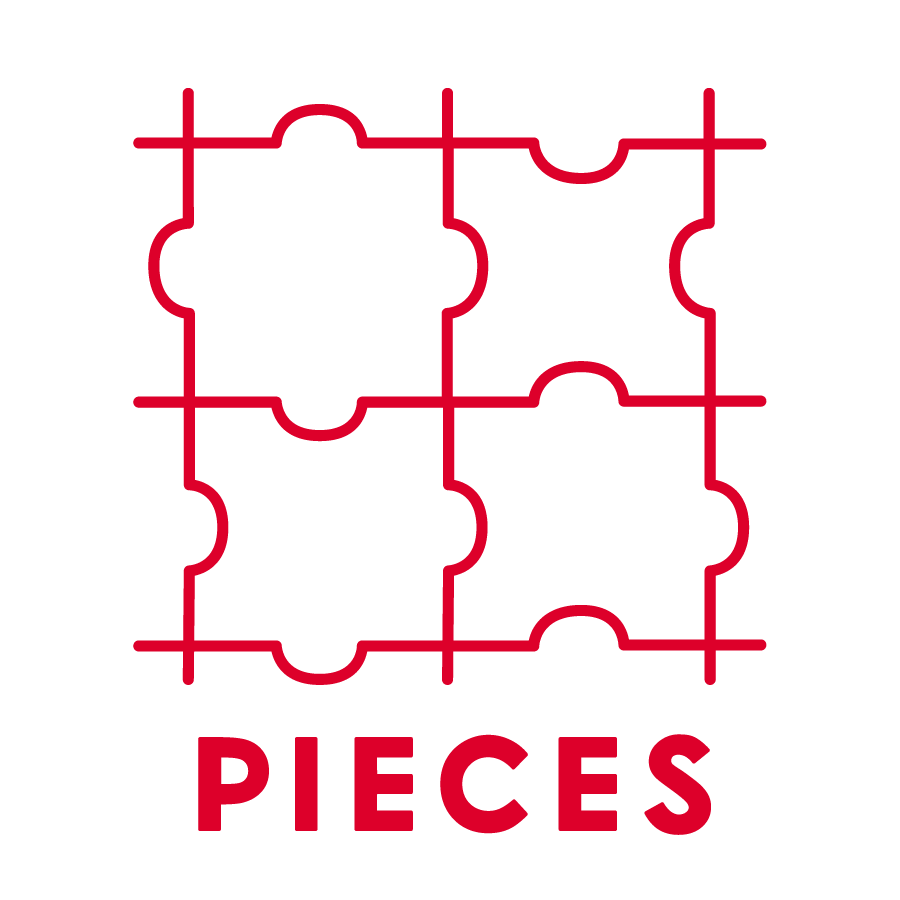SDGsの広まりなどを受け、社会課題解決に対する世の中の関心が高まりつつあります。「私にも何かできることがあるのだろうか」と考えたことのある方も多いのではないでしょうか。
子どもが孤立しない地域をつくるための市民性醸成を行う認定NPO法人PIECESと、「すべての人にチャンスを」をビジョンに、児童福祉をはじめ、様々な社会課題解決に取り組む認定NPO法人Living in Peaceの両代表による、オンライン対談が3月24日行われました。
2団体に共通するのは、社会を「特定の個人や団体ではなく、社会に暮らすわたしたち皆で変えていくもの」と考えていることです。そんな両代表が「社会をよりよい場所にしていくために大切なことは何か」についてお話しました。
団体紹介
まず、PIECES代表の小澤いぶき(以下:小澤)から、団体紹介がありました。
小澤:私は、心のケアを専門とする児童精神科医です。現場で出会う子どもたちを通して、この日本でも私たちのすぐ隣に痛みを抱えている子どもたちがたくさんいることを知りました。
子どもたちの周りには子どもの育つ環境があるけれど、その環境にいる人も痛みを抱えていたり、ひっ迫していたりして孤立していることがある。家族の相談を受ける機関もひっ迫しているという状況をたくさん見てきました。
子どもを取り巻く社会構造のひずみが、子どもたちにしわ寄せられています。その構造に対して、誰もが関わっているからこそ、一人ひとりの手から社会にはたらきかけていけるような土壌を耕していく必要があると思い、PIECESを立ち上げました。
相対的貧困は7人に1人、虐待相談対応件数約19万件(2019年度)、いじめの認知件数約54万件。貧困や虐待、不登校などの社会課題の背景にあるのは、子どもたちの心の孤立です。10人に3人の子どもが孤独を感じているとの報告もあります。孤立は、社会が生み出しているループです。
PIECESが目指し見つめているのは、時代を超えて子どもと共に優しい間を紡ぎ続ける社会です。優しい間というのは、互いに安全に頼り頼られる関係や、安全に自分の感情や欲求、願いを出せること。子ども自身やその子の背景に敬意を持ち、知ろうとし、想像力を持って尊重すること、関わりを問い直し続けていくことが優しい間には必要だと考えています。
社会に起こるさまざまなことを見つめ、受け取り、その上でさまざまにはたらきかけていく優しい間を紡ぐ力を私たちは市民性と呼び、市民性醸成プログラム(Citizenship for Children)という講座を全国へ広げています。皆さんがPIECESの想いに共感してくださり、何か自分にできることはないかと考えた時に、思い出していただけたら嬉しいです。
この講座は、子どもの環境を作っていくひとりの市民としてできることを考え深めていくプログラムです。座学にゼミと実践を加えて学び、子どものことはもちろんのこと、自分自身も大切にする方法を学んでいきます。
この講座から、例えば豊島区の若年妊婦支援プロジェクトである、project HOMEの前身となった「もえかんち」や、水戸市のコンビニオーナーさんが地域の子どもと話し合いながら、イートインコーナーをフリースペースとして開放し、地域の子どもたちの居場所にするなどの実践例が生まれています。現在、水戸市と奈良に続き、オンラインでの全国コースも開講しています。奈良のコースは今日登壇しているLIPさんと一緒に行っているものでもあります。
私たちは子どもたちが孤立の中で生き続け、社会のことを信頼できなくなる明日よりも、人の想像力から生まれる優しい間のあふれる社会を創りたいと願っています。マンスリーサポートなどでのご支援もよろしくお願いします。
続けて、認定NPO法人Living in Peace(以下:LIP)の代表理事、中里晋三(以下:中里)と龔 軼群(キョウイグン・以下:キョウ)が団体紹介を行いました。
中里:2007年にLIPは、主に途上国の貧困層、金融サービスにアクセスできず銀行口座を持てずにいる人へ、小口融資を行うマイクロファイナンス領域でのプロジェクトからスタートした団体です。
キョウ:村で小さなお店などをしていて、事業のためにお金が必要な一方、親類や高利貸しという選択肢しかなかった人たちに、日本の投資家から融資を募り、ミャンマーやカンボジアなど東南アジア諸国でこれまでに約2億3000万円規模のファンドを立ち上げてきました。
その後、2009年には、社会的養護の下で育つ子どもたちへ支援を行う、こどもプロジェクトを始めました。国内の児童養護施設や里親の元で生活する子どもたちの支援、子ども食堂などを行ってきました。2018年には難民プロジェクトという、日本国内の移民難民の支援をする活動を立ち上げています。
中里:LIPのビジョンは「すべての人にチャンスを」というものです。そして活動におけるモットーが「働きながら社会を変える」。LIPは現在150人ほどのメンバーで運営していますが、全員が他に本業を持ち、平日夜や土日を使ってパートタイムで活動しています。僕自身、普段は大学院で哲学を使いながら福祉を研究しています。
キョウ:私は株式会社LIFULLの社員ですが、住宅弱者の住まい探しをサポートするLIFULL FRIENDRY DOORという事業を通じてソーシャルアクションを起こしており、現在はその事業責任者も務めています。
もともと、上海から5歳で来日した移民なので、日本社会での外国人という異物感や不平等を肌で感じてきました。そんな経歴も手伝って、LIPでマイクロファイナンスプロジェクトや難民プロジェクトに関わっています。
ソーシャルアクションは、企業の中でもNPOでも、どちらでもやろうと思えばできることです。LIFULLでは最初ひとりでソーシャルアクションを始めましたが、徐々に仲間が集まって来て、いつの間にかキャリアにもなっていました。社会に対してできることを探している人へ、一例として参考にしてもらえればと思います。
中里:ちょうど今年に入って、「移民・難民の子どもたちのいのちを守る基金」という、生活保護利用の困難な外国籍子育て世帯向けの緊急支援を始めました。第一弾を終え、第二弾の実施に向けたクラウドファンディングを行っています。寄付という行動も社会を変えるアクションの一つです。ぜひご支援をご検討ください。
ひとりの市民としてできるソーシャルアクションとは?
ークロストークセッション
今の活動に至った背景
キョウ:会社に入ったとき、フィリピンのスモーキー・マウンテンを支援するNPOで、ボランティアをしていました。そのNPOのスタディーツアーでフィリピンに行ったとき、LIPの理事もそのツアーに参加していて。そのときにLIPのことや、NPOの一員として事業を創ることのできる場所があると知り、2015年にLIPに入りました。
また、自分自身が当事者として「入居差別をなくしたい」とずっと思っていたので、LIFULLに入って社会課題解決の新規事業を2016年に立案しました。それが今LIFULL HOME’SのSDGs事業として成り立っています。
小澤:山梨の田舎出身で、人よりも虫や動物や木の方が多い中で育ったことが背景にあります。森ではそれぞれが存在しながら補い合っています。でも、その中で毛虫という理由だけで、人に毛虫が踏みつぶされることに衝撃を受けました。
その後、戦争関係のアニメや映画を見て、自然に対してしていることが、人の世界でも起こっていると知り、「どうしてこんなことが起こるのか」と思うようになりました。「どうして同じ地球に生きていて、たまたま生まれた場所が違うだけで、こんなにも環境が変わってしまうのだろう」と子どもの頃から感じていました。
中里:LIPに入った経緯は、本当に偶然ですね。「少し社会科見学をしてみようかな」くらいの気持ちで、NPOのミーティングに入ったら、深夜になってもメール上での熱い議論が延々と続いて終わらないということがあって。「その雰囲気って何だろう」と思ったのが、最初のきっかけです。
それと、今もそうですが、LIPはフラットでした。僕自身、何らスキルを持っていない中で、対等に扱ってもらえた経験がすごく大きかったです。対等に扱ってもらえる場所に出会えたことが、自分を次のステップに押し上げてくれる力になったのだろうなと思いますね。
活動する中で感じた市民の力
キョウ:アクティボ(activo)というボランティアサイトで、1年前くらいからLIPの掲載を始めたら、ボランティアをする人がすごく増えました。いろんな人がフラットにLIPの見学に来てくれるようになったんです。見学者も2倍以上になったのではないかと思います。
それは、活動に興味関心があって「自分も何かやってみよう」と思う方々が増えているということだと思います。ボランティアの皆さんのおかげで、LIPの事業も広がってきていると感じます。
中里:コロナの影響で、全てのミーティングをオンラインでするようになったことで、今までだとオフィスに来るのが難しかった方が、LIPに入ってきてくださって。子育てをしていて、その経験や思いを行動に移したいという方も随分増えました。議論の豊かさが変わり、とても大きな変化を感じています。
また、子どもに関わるお兄さん、お姉さんの関係は、仕事として関わるという文脈では、できないことの一つだと思っていて。でも、すごく大事なことですよね。同じことを子どもに言うとしても、伝わり方が全然違う。それは市民の力の一つなのだろうなと思います。
小澤:PIECESでは「この地球をともにしていて、何かが起こったときに、それを見つめて受け取り、働きかける人たち」を市民と言っています。私はひとりの市民でもあり、専門職としてもトラウマケアに従事しています。心に傷がついて、専門的なケアが必要になったとき、日常の安全がすごく大事です。
その安全を作っているのは、地域に暮らす人々です。専門機関の関わりは、どうしても終わりがありますが、地域の人との関わりは終わりがなく、自分でどうしたいかを関わりの中で選んでいけるのではないかと思うのです。
また、間接的な関わりも含め、誰が制度を必要としているかに気付いたり、実際に制度が地域の中で実践されていったりするのにも、市民の力が必要です。
ソーシャルアクションの一歩目
キョウ:生活の中で当たり前になっているものに、誰かが困っていないかと考えてみる。それがソーシャルアクションの一歩目ではないかと思います。そのことが、次にどうしたら良いかにつながっていくと思います。
小澤:他者のことを想像する力でもあるのだろうなと思いました。知らないことがあることを知りながら、人と出会うことが、さらに想像力を耕すのだろうなと。
キョウ:「出会いに行く」ことも大事だと思います。実際に出会いに行くことで、その人の困りごとについての想像がどんどん広がって、何が必要かを考えることができると思います。フィリピンのスモーキー・マウンテンに行かなければ、LIPを知ることはなかったと思います。
小澤:子どもたちは時に出会いに行かないと出会えないことがあるなと思いました。小さければ小さいほど、子どもたちは周りの大人を介して社会につながっています。出会いに行って初めて、解像度高く、その子の生活の実態を知ることができると思いました。
中里:第一歩はおそらくそれぞれ違うものとして、全ての人の身近なところにあるはずですよね。
LIPではいろんなメンバーとの出会いが、「こういうことができるな」と気づいたり、自分になかった視点を与えてもらったりするきっかけになります。その中で、チームで問題解決の方法を考える循環が生まれてくると思います。
だから、出会いがおそらく出発点だと思います。そしてその出会いに、心地良さと感じたり、ワクワクしたりすることが、一歩目を踏み出す大事なサインじゃないかと思います。
小澤:出会いによる面白さの中に、自分が持っていないメガネを知れることがあると思います。それで、気づきのポイントが増えていくことはありそうだなと思いました。
周りで起こっている出来事に関心を向けて、私の範囲がどんどん広がっていくと、自分の日常や、海外などの遠くだと思っていた日常にも、アクセスできるようになるのかなと感じました。
ソーシャルアクションの一歩目のかけらは、日常の中にたくさん見つかると思います。寄付をすること、周りの出来事に関心を持って発信をすることなども、できることの一つです。
中里:それぞれの立場から、問題をマクロの視点で捉える、また身近なところからミクロの視点で捉えるという仕方があって。ソーシャルアクションの起こし方は、ひとりの人の中でも固定したものではないですよね。
小澤:大きな制度にはたらきかけていくアクションから、日常をつくっていくアクションまで、どれもが必要で。ミクロとマクロを行き来できることが、すごく大事なことだと思います。
キョウ:自分の中で生まれた問題意識に目を向けるだけでも、それはソーシャルアクションだと私は思っています。
一方で、日常ではカバーしきれない、制度からこぼれ落ちてしまう人たちがいます。そのことを知っても、自分とのつながりを感じづらいこと、その人たちの立場に立って想像してみることの難しさは、往々にしてあるなと思って。
社会から取り残されている人たちがいることをちゃんと認識して、そこに対してアクションを起こすために、価値観を変えていくことも、もしかしたら必要なのかなと思っています。
ソーシャルアクションの一歩目は、私たちの日常の中にあります。
困っている人がいないか想像してみること、自分から人に出会いに行くこと、寄付をしてみること、周りの出来事に関心を持って発信すること、社会問題に目を向けることなど、私たちができることはたくさんあります。
ひとりの市民として、自分にできることを探してみること。そのことが、日常の安全を紡ぎ、子どもたちの暮らす社会が、より良い場所になることへつながっていきます。あなたの小さな一歩が、社会にとって大きな一歩になります。
今回の対談が、あなたの背中をそっと押し、新たな一歩を応援するきっかけになることを願っています。
2021.04.12
執筆:麓 加誉子・田中 美奈